|
初秋の京都から若狭・近江湖北へ
|
2011・10・24〜26
|
|
十一面観音を訪ねてきました。
仏像ばかりでなく古刹や歴史に至るまで憧憬の深い友人達の
中で私は恥ずかしながらの にわか勉強付け焼き刃でしたが
以前から白洲正子を読んでいた家内もお願いして6名の旅と
なりました。
紅葉にはひと月ほど早い時期でしたが、それだけに何処も静かで
落ち着いた初秋の旅でした。
|

|
|
|
|
|
|
|
|
京都大原の里

|
|
大原を訪れたのは30年も前になります。
すっかり記憶も薄らいでいましたが、来てみると「やはり変わっていない」と感じるところが嬉しくて
里の人々に感謝するばかりです。
三千院も紅葉のハイシーズンを前に訪れる人も少なく、静かな空気が流れていました。
「 苔は衰えた母体の上に新たな生命を乗せます。それを繰り返し永い年月をかけてこのように
ふっくらとなるのよ 」
何気ない家内の説明なのですが、なにかやるせなさを感じるのは「歳」のせいでしょうか。
|
|

|

|
|
|
|
旅の初日は皆それぞれが自由行動です。
我々が大原行きを決めたのは宝泉院の庭が目的でした。
三千院から少し歩くと大原天台宗の中心勝林院となり、宝泉院はその僧坊でありながらJR東海の
「そうだ 京都 行こう」で評判となり本家よりも人を集めています。
 お茶代込みの拝観料を払い、上がるとすぐに緋毛氈の お茶代込みの拝観料を払い、上がるとすぐに緋毛氈の
広縁に案内され抹茶がふるまわれます。
額縁の絵のような樹齢七百年の五葉松や竹林を前に
すっかり良い気分になっていると間を計ったように
住職が現れ
「天井に気がついたか?戦国の世に伏見城で自害した
武将達の血をたっぷりと吸った床板を天井板にしている。
これが血溜まり。割腹で出た内臓の染み。かきむしった
爪の傷。 そしてこの目玉の跡 が皆さんを上から見ているのだよ」 と ニヤリ。
そして最後は「 お茶は うまかったか?」とくる。 はじめてお茶代込み拝観料の意図がわかったのです。
|
|
|
|
昔どうりの大原も寂光院は大きく変わっていました。
10年前の放火で、本堂もお地蔵様さまも建礼門院像も焼失し石の階段のアプローチと寺を取り巻く
境内、そして心字池だけが昔の面影を残すばかりです。
聖徳太子・地蔵菩薩・平家物語と悲しい歴史の尼寺のなんとも腹の立つまた痛ましい話です
少し寒くなった夕暮れの大原を「ベニシアは何処にいる」と思いながら京都に戻りました。
|
|

|

|

|
|
「 左京道右寂光院の標あり すなはち右に坂登りゆく 」 岡野 直士郎の歌
|
|
|
|
美山 かやぶきの里
|
|

|
|
|
江戸時代 京都から若狭の交通要路の一つ「鯖街道」とも言われた162号線を北山の杉林を見ながら
北へ2時間半ほどの走り、街道を少し外れたところに美山はありました。
車を降りると駆け出したくなるような懐かしい風景が広がり、疎開を山形で過ごした家内は大喜びです。
年暮れた雪の夕べであれば与謝蕪村の墨絵「雪の暮れ」そのままの景色です。
緩やかな坂道に沿って続く38戸のかやぶき屋根の家々は、折からの赤い柿の実やコスモスに囲まれて
「昔々あるところに・・・・」を思い出させるような心和む村でした。
トタン屋根を茅葺に直した家もあるとのこと。 いつまでも残してほしい日本の風景です。
|
|

|

|
|

|

|
藍染工房
村の中ほどに京都から来て30年という
藍染職人が工房を開いていました。
絞り装置まで考案し独特の技術で素晴
らしい作品をもとの二階蚕部屋に展示して
いました。
京都の都市化で染めに必要な水が不足
し美山の自然と風景に魅されて移ってき
た と話してくれました。
|
|

|
|
|
|
若狭小浜(おばま) 伝説の里
|
|

|
|
一見めずらしくもない谷川ですが、ここが若狭の悠久のロマンが
息ずく場所 「鵜の瀬」です。
話によると・・
奈良平城京の時代 東大寺大仏開眼供養に呼ばれた若狭の
神様が釣りに夢中になり、なんと法会に遅刻しました。
その罰として東大寺二月堂「お水とり」の聖水を毎年この場所から
送らされる羽目となり、以来 千二百年にわたり毎年3月2日の
深夜「お水おくり」の行事が行われてきたのです。
|

|

|
|
いかに ご先祖さまのうっかりとはいえ末裔の皆様が、厳寒の山深い谷川で今後とも果てしなく償いを
継承してゆかねばならぬとは本当にご苦労様です。
10日後奈良に水が届くという伝説と共に、毎年 大松明の僧列や大護摩の炎の祭典で「鵜の瀬」は
大変な賑わいとなるそうです。
ことの起りが 「遅刻」 による悠久の行事とはなんとも愉快で日本的でいいですね。
|
|
|
|

|
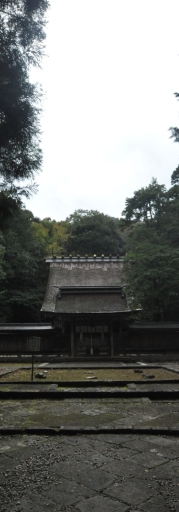
|

|

|

|

|
|
名物の焼き鯖 伝統の塗箸 そしてNHN朝ドラ「ちりとてちん」の舞台でもある小浜は古来より朝鮮との
接点であり、南北朝時代以降は南蛮交易も盛んで近世には北前船の寄港地として栄えたといいいます。
大河ドラマ「江」の姉 お初もここ若狭京極高次の妻であり、なぜか今年の旅はドラマの舞台が多いのです。
若狭彦神社 若狭姫神社 そして多田寺十一面観音 神宮寺千手観音 明通寺の国宝三重の塔を巡り
小浜の町に着いたのは夕刻でした。
折から風雨が強くなり若狭湾のしぶき飛ぶ中を町に出ました。
6時前というのに店じまいが早く、暗く寒い陰気な街を空腹で歩き、やっと行きついた飲み屋さんの温かい
赤提灯に、すっかり北日本を感じながら「思えば遠くまで来たものだ」と小浜名物で乾杯です。
|
|

|

|
|
晴天の翌日 羽賀寺を訪ねました。
昨日歩いた寺や神社は「鵜の瀬」を経てこの羽賀寺に至り若狭湾に入る遠敷川の流域に点在します。白洲正子は「若狭に十一面観音が多いのは水の信仰と無関係ではない」と書いています。
|
|
|
この日 羽賀寺は訪れる人もなく案内を請うても寺の人も見えず、しばらくたって若い女性が現れ説明を
頂きました。 淡い燈明に浮かんだ十一面観音は色鮮やかに古色を残し、千三百年の年月を感じさせない
美しいお姿です。都から遠くこのような僻地と素朴な寺で、よくここまで残されていたものだと感じ入りました。
|
|
湖北・木之本 観音の里
|
|

|
|
初めて渡岸寺の国宝十一面観音像を拝したのは三年前の紅葉真っ盛りの頃でした。
またお会いしたいと思いながらの再会です。 そして不思議なことに約2メートルの背丈を今回はなぜか
|
|

|

|
小さく見えたのは、2度目の拝顔でその存在を
いくらか身近に感じられるようになった為でしょうか。
元来 仏像は両性具有と言われていますが観音様は
女性であると私が勝手に思い込むようになったのは
この像に会ってからです。
肩の張りはすこし大きいですが流れるような胸から
腰にかけての線はまさしく女性であり、頬のふくらみ
や伸びやかな指先などは男性ホルモン(・・があれば
ですが)のなせるところではありません。
凛とした美しいお顔の真裏に「大笑面」の化仏の嫌味
な笑い顔を隠しいるところなど、やはり女性であること
の表れではないでしょうか。
現代は男も女も両性具有が多くなってきたようです・・
とお伝えして渡岸寺を後にしました。
|
|

|
|
|
近畿東海北陸の交差要路である湖北は古くから商業・文化・宗教の大いに栄えた所であり、今も多くの寺と十一面観音や千手観音が多数残されています。
しかしそれぞれの時代の戦火や宗教的変遷などによる廃寺も多く、現在でも里人が交代で観音様をお守りしている寺が多数あります。
|
|
|
|

|

|

|
|
最後に訪ねた石道寺も村のおじさんがひっそりと当番をする小さなお堂でした。
こちらの十一面観音は何とも可憐なお姿で、井上靖は小説「星と祭」でこう書いています。
「この十一面観音さまは村の娘さんの姿をお借りになって、ここに表れていらっしゃるのではないか。
素朴で優しくて・・・・野の匂いがぷんぷんする。」
|
|
小説では娘を湖で亡くし心定まらず観音巡りをする父親が 「湖北の観音様はみな琵琶湖を向いて
おられる」と話すくだりがあります。湖に眠る娘を湖畔の観音が見守ってくださると信じた時に、自ら心の整理を付けて小説は終わります。観音を巡りながらそれを守る里の人々との対話を重ねてゆくうちに
父親が次第に心を落ち着けてゆく様子が見事でした。
湖北から米原に走り我々の旅は終わりました。
京都から美山、小浜 湖北と巡り楽しい仲間と内容のある三日間でした。
そして里人が信仰を超えて仏像を守り続けることを生活の中に取り込み、そして見守られている豊かな
関係を目の当たりにし、なにか忘れていたような事を思い出させる旅となりました。
(仏像その他撮影禁止の画像はパンフレットなどから転写しています)
旅TOPへ戻る
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|